「犬が死んだらどうする?」手続きや葬儀について獣医師・ペット葬のプロ監修
2018.10.18 いぬ , お悔やみ , ペットが亡くなったら目次
愛犬が亡くなった際に飼い主がすべきこと
愛する犬との突然の別れは、飼い主にとって計り知れない悲しみをもたらすものです。しかし、その悲しみの中でも、大切なペットを安らかに送り出すために飼い主がすべきことはいくつかあります。具体的には、亡くなった直後の対応、火葬と供養、そして各種手続きの3つの側面から、後悔のないお見送りのための情報を解説していきます。
この記事の監修者:イオンペット株式会社 獣医師 鈴木 信吾 先生/大森ペット霊堂(東京都大田区) 齋藤 鷹一 さん
犬の死亡を確認する方法
犬が動かなくなったとき、「もしかして…」と感じても、すぐに死を判断するのは難しい場合があります。実際には仮死状態や意識障害の可能性もゼロではありません。
夜間や休日などですぐに診てもらえない場合などは、以下の点を確認してください。
呼吸が完全に止まっているか
胸やお腹の上下運動がまったく見られないかを確認します。心拍・脈が感じられないか
胸に手をあてたり、内腿の付け根(大腿動脈)で脈が取れないかを確かめます。瞳孔が開いたままで光に反応しないか(対光反射の消失)
暗い部屋でペンライトなどを使い、瞳孔が収縮しないかを確認してください。犬の死亡確認は獣医師が行うことがもっとも確実な方法ですが、もしご自身で行う場合はまずは上記3点だけでもしっかりと確認してください。
(獣医師:鈴木 信吾 先生)
犬の死亡に際しては死亡診断書などは法的な義務はないものの、加入していたペット保険の請求手続き、ごく一部の自治体やペット火葬場で求められる場合がありますので獣医師による死亡診断を受けると確実です。
亡くなった直後の対応
愛犬が亡くなった直後は、深い悲しみと動揺からどうすればよいか判断に迷うかもしれません。しかし、大切な愛犬を安らかな姿で送り出すためには、いくつかの対応が必要です。まずは気持ちを落ち着かせ、愛犬の体に「ありがとう」と感謝の言葉をかけてあげましょう。
遺体の安置方法
愛犬の遺体を安置する際には、まず遺体を清めることから始めましょう。お湯で湿らせたガーゼやタオルで全身を優しく拭き取り、毛並みや尻尾を整えます。死後に口や肛門から体液が出ることがあるため、ガーゼや脱脂綿を詰めて清めると良いでしょう。
これは人間でも起こる自然現象であり、心配する必要はありません。次に、死後硬直が始まる前に手足を丸めて、生前のリラックスした姿勢に整えてあげます。死後硬直は亡くなってから2~3時間ほどで始まるため、早めの対応が重要です。硬直してしまうと関節が外れてしまう可能性があるので注意が必要です。
遺体を清潔に保つためには冷却が不可欠です。遺体の下に厚手のタオルを敷き、ドライアイスや保冷剤を直接触れないようにタオルで包んで、首回りやお腹周りを中心に置きましょう。ドライアイスは葬儀業者に依頼するか、通販サイトでも購入できます。
体に水分が残ると腐敗が進みやすいため、しっかり水分を拭き取ることが大切です。夏場に何日か安置する場合は、エアコンの効いた部屋で、なるべく低い温度に設定して遺体を保ちます。
段ボールや木製の箱に、毛布やバスタオルを敷いて安置し、体液が漏れる可能性に備えてビニールシートや新聞紙を敷いておくと安心です。生前愛用していた毛や花、おもちゃなどを棺に一緒に入れてあげることもできますが、素材によっては火葬に適さない場合もあるため、事前に火葬業者に確認しましょう。
目と耳は最後に機能が失われると言われているため、最期の瞬間まで優しく話しかけたり、安心させる言葉をかけ続けることが、愛犬にとって安心感をもたらし、飼い主としても最後の愛情を示す行為となります。
最期の過ごし方
愛犬の死期が近づいた際、飼い主としてできる最も大切なことは、悔いのない時間を共に過ごすことです。
愛犬が不安を感じないよう、慌てずに最期のときを見守りましょう。死期が近づくと、食欲不振や活動量の低下、排泄のコントロールが難しくなるなどの兆候が見られることがあります。そうした状況でも、できる限り愛犬が安らかに過ごせるように、普段の生活と変わらず接してあげることが重要です。
愛犬が安らかに旅立てるよう、可能な限り一緒に過ごす時間を作り、感謝の言葉を伝えましょう。また、愛犬が好きだった人や、犬をたくさん可愛がってくれた友人に会いに来てもらうことも、心の準備をする上で役立ちます。
飼い主自身が寂しい気持ちでいる場合は、感情を共有し、支えを求めることも大切です。愛犬との別れは辛いですが、後悔を残さないためにも、できる限りのことをしてあげましょう。
火葬と供養
愛犬との別れにおいて、火葬は多くの飼い主が選択する重要なステップです。火葬後の供養方法も多岐にわたり、飼い主の気持ちや状況に合わせて選択できます。
火葬方法の種類
犬の火葬方法には、大きく分けて以下の4種類があります。多くの火葬業者や霊園では、これらの方法の中から選択できるため、それぞれの特徴を理解し、大切なペットをどのように見送りたいかを検討しましょう。
「合同火葬」は、他のペットと一緒に火葬される方法です。複数の遺体をまとめて火葬するため、費用を抑えることができますが、遺骨が混ざり合ってしまうため、返骨はされず、共同の慰霊碑などに埋葬されるのが一般的です。
「個別一任火葬」は、ペットを業者に預け、個別に火葬してもらう方法です。飼い主が立ち会うことなく火葬が行われ、後日遺骨を引き取ることができます。精神的な負担を軽減したい場合や、立ち会う時間がない場合に選ばれています。
「個別立ち会い火葬」は、火葬から収骨まで、飼い主が立ち会って行われる方法です。人間の葬儀に近い形で、愛犬との最期を丁寧に看取りたいと考える飼い主に多く選ばれています。火葬後すぐに遺骨を持ち帰ることができ、その後の供養も自由に選択できます。
ペット霊園で犬の立会い火葬をする場合の流れ
愛犬との最期のお別れをきちんとした形で迎えたいと考える飼い主には、「個別立会い火葬」を選ぶ方が多いです。「イオンのペット葬」においては約70%のご家族さまが個別立会い火葬をご選択されています。(24年1月~6月実績)
ここでは、ペット霊園で犬の立会い火葬を行う一般的な流れをご紹介します。
ペット霊園での立会い火葬の流れ(例)
-
予約・電話連絡
まずはペット霊園に電話またはWebで予約をします。希望日時や火葬方法(立会い/一任)を確認されます。お花の用意や、棺に入れられるものなど確認するといいでしょう。 -
来園・受付
当日、霊園へ愛犬を連れて行き、受付を行います。プランの最終確認や火葬費用の支払いなどを行います。 -
お別れの時間(セレモニー)
専用の部屋で、ご家族だけの静かな時間を過ごします。棺にお花や手紙、お気に入りのおもちゃなどを納めることができます(※地域条例などの理由からペット霊園により異なるため要事前確認)。 -
火葬
専用のペット火葬炉で火葬が行われます。小型犬で約40~60分、大型犬で120分程度が一般的です。火葬中は待合室で休憩することも可能です。 -
お骨上げ(拾骨)
人間と同様に、火葬後に遺骨を拾い上げて骨壺に納めることができます。ご家族全員で丁寧に行うことが多いです。 -
ご返骨・納骨の選択
遺骨は持ち帰ることもできますし、霊園の納骨堂・合同慰霊碑に納めることも選べます。
立会い火葬は、感謝の気持ちを形にして送り出せる最も丁寧な方法です。
また、ご家族の気持ちの整理や、お子さまにとっても命の重みを実感する機会にもなります。(大森ペット霊堂 齋藤 鷹一さん)
火葬後の供養方法
火葬後、愛犬の骨をどのように供養するかは、飼い主それぞれの気持ちと状況によって様々な選択肢があります。法的な決まりはないため、後悔のない供養方法を選びましょう。 最も一般的なのは、骨壺に納めた遺骨を手元に置いて供養する「手元供養」です。
自宅に安置することで、いつでも愛犬の存在を身近に感じ、生前の思い出を振り返りながら供養することができます。また、自宅の庭に埋葬することも選択肢の一つです。広い庭がある場合や、自然に還してあげたいと考える飼い主に選ばれています。
ただし、マンションやアパートなどの集合住宅では難しい場合があるので注意が必要です。より自然な形での供養として「散骨」も挙げられます。これは、遺骨を粉状にして海や山に撒く方法です。個人で行うのは難しいため、専門業者に依頼することが推奨されます。ペット霊園に納骨することもできます。
多くのペット霊園では、火葬から納骨、埋葬まで一貫してサービスを提供しており、定期的な慰霊祭や法要を行う施設もあります。他にも、遺骨の一部をアクセサリーにして常に身につけたり、分骨して異なる場所で供養したりするなど、多様な供養方法があります。(大森ペット霊堂 齋藤 鷹一さん)
どの供養方法を選ぶかは、家族でよく話し合い、愛犬の性格や家族の生活状況なども考慮して決めると良いでしょう。
各種手続き
愛犬が亡くなった際には、心のケアと共に、いくつかの実務的な手続きも必要となります。特に犬の場合、狂犬病予防法に基づき、行政への死亡届の提出が義務付けられています。
市役所への死亡届提出
犬が亡くなった場合、狂犬病予防法により、死亡後30日以内に市町村長への死亡届の提出が義務付けられています。 この手続きを怠ると、狂犬病予防法に違反する可能性があり、その結果、20万円以下の罰金が科される場合があります。
死亡届の提出には、愛犬を登録した際に交付された犬鑑札や狂犬病予防注射済票、および死亡届の用紙が必要です。 提出先は自治体によって異なり、市役所の窓口、保健所、または環境衛生課などが一般的です。 郵送やオンラインでの提出に対応している自治体もあります。
マイクロチップを装着している犬の場合、環境省指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」での手続きも必要となります。 狂犬病予防法の特例に参加している自治体では、マイクロチップの情報登録によって市役所への手続きが不要となる場合があります。 血統書がある場合は、血統書登録団体への抹消手続きも検討しましょう。
その他の手続き
愛犬が亡くなった際の手続きとして、市役所への死亡届提出の他に、獣医師からの死亡診断書の発行を依頼することが考えられます。これは、火葬業者によっては提出を求められる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。
また、加入していたペット保険がある場合は、死亡に伴う保険金の請求手続きが必要になります。保険会社に連絡を取り、必要な書類や手続き方法を確認しましょう。複数のペットを飼育している場合や、今後もペットを飼う予定がある場合は、かかりつけの病院への連絡も忘れずに行いましょう。
仕事を休む際の考慮事項
愛犬が亡くなった際の手続きとして、市役所への死亡届提出の他に、獣医師からの死亡診断書の発行を依頼することが考えられます。これは、お住いの自治体や火葬業者によっては提出を求められる場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。また、加入していたペット保険がある場合は、死亡に伴う保険金の請求手続きが必要になります。
保険会社に連絡を取り、必要な書類や手続き方法を確認しましょう。複数のペットを飼育している場合や、今後もペットを飼う予定がある場合は、かかりつけの病院への連絡も忘れずに行いましょう。
休暇の取得方法
ペットの死は、労働基準法上の忌引き休暇の対象にはならないのが一般的です。忌引き休暇は、三親等以内の親族の不幸に適用されることが多いため、ペットのために仕事を休む場合は、年次有給休暇や欠勤として取得することになります。
近年では、ペットも家族の一員と考える人が増えていることから、「ペット忌引き休暇」や「ペット休暇」を独自に設けている企業も一部に存在します。会社の就業規則を確認し、もしそのような制度があれば積極的に利用を検討しましょう。
有給休暇であれば、原則として休む理由を会社に伝える必要はありませんが、必要に応じて回答することも考慮しましょう。
職場への伝え方
仕事を休む理由を職場に伝える際は、正直に伝えるか、あるいは体調不良や家庭の事情として伝えるか、職場環境や人間関係によって判断が分かれます。「家族の一員を失い、心身ともにダメージを受けているため、数日間休ませていただきたい」と正直に伝えることで、理解が得られる場合もあります。
その際は、休む日数や仕事の引き継ぎ計画もあわせて伝えることが大切です。しかし、ペットの死に対する理解がまだ浸透していない職場では、「急な体調不良」や「私用」といった表現を使うことも一つの方法です。どのような伝え方をするにしても、無断欠勤は避け、必ず連絡を入れることが社会人としてのマナーです。休んだ後は、業務をフォローしてくれた上司や同僚に感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。
お子さまがいる家庭での心のケアと向き合い方
愛犬との別れは大人にとっても辛いものですが、小さな子どもにとっては「死」そのものを初めて体験する重大なできごとです。
以下のような対応を取ることで、悲しみを分かち合いながら、命の大切さを学ぶ機会にもつながります。
-
一緒に手紙を書いて棺に入れる
-
火葬・お葬式に家族で参加し、感謝を伝える
-
思い出を話す時間をつくる(写真や動画を見ながら)
「泣かないで」と抑えるのではなく、「悲しいね」「寂しいね」と共感しながら寄り添うことが、お子さまの心の成長にもつながります。
(大森ペット霊堂 齋藤 鷹一さん)
(まとめ)愛犬との最後の時間を後悔のないものに
愛犬の死は、飼い主にとって深い悲しみと混乱をもたらすものです。しかし、その大きな喪失感の中でも、飼い主としてできることはたくさんあります。遺体の安置や火葬・供養の準備、行政への手続きや心のケアまで、一つひとつを丁寧に行うことで、「ありがとう」を伝える時間に変えていくことができます。
最期まで愛犬と向き合い、できる限りのことをして送り出すことは、自分自身の心を癒す時間にもつながります。ペットも家族の一員。後悔のない見送りのために、本記事の内容を参考に、必要な準備と手続きを落ち着いて進めていきましょう。
最新記事 by イオンのペット葬 (全て見る)
- メダカが底に沈む?原因と初心者でもできる対策法 - 2025年7月16日
- トイプードルの寿命はどのくらい?平均や死因について解説 - 2024年5月29日
- 老犬の痙攣の原因と対処法は?余命宣告で飼い主にできることも解説 - 2024年5月29日
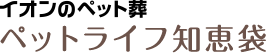

 悔いのない別れのために必要なこと
悔いのない別れのために必要なこと ハムスターが死んだらする3つのこと (獣医師・ペット葬儀のプロ監修)
ハムスターが死んだらする3つのこと (獣医師・ペット葬儀のプロ監修) ペット葬儀-お悔やみの花-ベスト5
ペット葬儀-お悔やみの花-ベスト5 ペット葬儀の選び方
ペット葬儀の選び方
