ペットの49日とは?意味と供養方法を解説
2025.8.29 ペット供養目次
ペットにも49日の供養は必要ですか?
はい、ペットにも49日の供養を行うことで、気持ちの区切りをつける意味があります。
仏教では、人が亡くなると49日かけて魂が旅立つとされています。その考え方をもとに、ペットにも「49日法要」を行う飼い主が増えています。必ずしも宗教的な義務ではありませんが、感謝やお別れの気持ちを形にする大切な機会です。
供養の方法はさまざまで、お坊さんを呼んで読経してもらう方法、自宅で家族だけで手を合わせる方法などがあります。どの形式が正しいというものはなく、飼い主の気持ちを大切にすることが一番です。
ペットの49日はいつ行えばいい?
亡くなった日から数えて49日目に行います。
人間と同じく、ペットの49日も「亡くなった日を1日目」として数え、49日目に供養するのが基本です。ただし、仕事や家族の都合で前後にずらしても問題ありません。
大切なのは日にちよりも「心を込めて供養する」ことです。日程を調整する場合は、命日や週末にあわせて行う方が多いです。
49日には何をすればいい?
読経やお供え、自宅での祈りが一般的です。
ペットの49日法要では、以下のような供養方法が多く選ばれています。
- お寺や霊園でお坊さんに読経をお願いする
- 自宅に遺影や骨壷を置き、家族で手を合わせる
- 花やおやつ、好きだったおもちゃを供える
- 好物やごはんを少し用意して偲ぶ
特別な形を整えなくても、家族で心を込めて祈るだけでも十分な供養となります。もし正式な法要を希望する場合は、ペット供養に対応した寺院や葬儀社に相談しましょう。
お坊さんを呼んで法要してもらえる?
はい、ペット専用の法要を受け付けている寺院があります。
最近では、ペット供養を積極的に行う寺院や霊園が増えています。49日法要ではお坊さんによる読経や、納骨堂での供養も可能です。料金は1〜5万円程度が相場ですが、場所や内容によって異なります。
探す方法の一例:
- 「地域名+ペット供養」で検索
- ペット葬儀社に相談して紹介してもらう
- 動物霊園のサービスを利用する
人間同様にしっかりとした形で見送りたい方にはおすすめです。
49日後に遺骨はどうするのが一般的?
納骨・散骨・自宅安置などの選択肢があります。
49日を区切りに、遺骨の行き先を決める方が多いです。主な方法には以下があります。
- ペット霊園や合同墓に納骨:他のペットと一緒に眠れる安心感がある
- 納骨堂に預ける:いつでも会いに行ける利点がある
- 自宅に安置する:そばに感じられるため選ぶ飼い主が多い
- 散骨する:思い出の場所や自然に還す選択肢
どれを選んでも間違いではなく、飼い主と家族の気持ちを一番に考えることが大切です。
まとめ
ペットの49日は「義務」ではなく、「区切り」と「感謝の気持ち」を込めるための儀式です。亡くなった日から49日目を目安に、読経やお供え、自宅での祈りなど、飼い主に合った方法で供養を行うとよいでしょう。
お坊さんを呼んだ正式な法要から、家族だけで静かに祈る形まで選択肢は多様です。また、49日を節目に遺骨の行き先を決める方も多く、納骨・散骨・自宅安置など自由に選べます。
大切なのは形式よりも「ペットへの想いを大切にすること」。自分たちが納得できる供養の形を選び、心穏やかにペットを見送ることが何よりの供養になります。
最新記事 by イオンのペット葬 (全て見る)
- ペットの49日とは?意味と供養方法を解説 - 2025年8月29日
- ペットが死んだら保健所に届け出るべき? - 2025年8月29日
- 愛犬が死んだらすべきこと|飼い主が取るべき対応と手順 - 2025年8月29日
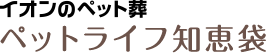
 ペット葬儀「イオンのペット葬」のこだわり
ペット葬儀「イオンのペット葬」のこだわり ペットが亡くなった後、火葬する人は約76%⁉
ペットが亡くなった後、火葬する人は約76%⁉ ペットのお葬式に香典は不要!どうしても香典を渡したい時のおすすめ
ペットのお葬式に香典は不要!どうしても香典を渡したい時のおすすめ ペットのお墓を庭に作る際の流れや注意点を解説
ペットのお墓を庭に作る際の流れや注意点を解説
