犬アレルギーの症状と原因!愛犬と仲良く暮らしていく方法
2020.6.15 ペットコラム
犬アレルギーは、どんな人にも起こる可能性があります。
もしも犬アレルギーになってしまったら、どのような対策が必要なのでしょうか。
今回は、犬アレルギーの症状や発症した時の対処法などをご紹介します。
目次
1.犬アレルギーとは?そのメカニズムと意外な発症要因
犬アレルギーは、犬のフケ、唾液、抜け毛、尿などが持つ特定のタンパク質を体が「異物」と認識し、過剰な免疫反応を起こすことで発症するアレルギー症状です。花粉症と同じように、アレルゲンが体内に入ることでヒスタミンなどの化学物質が放出され、様々な症状を引き起こします。
犬アレルギーの主なアレルゲンは、実は犬の毛そのものではなく、毛に付着しているフケや唾液、皮脂に含まれるタンパク質です。特に「Can f 1」と呼ばれるタンパク質が最も一般的な犬アレルゲンとして知られています。このタンパク質は、すべての犬種で分泌されており、たとえ抜け毛が少ない犬種であっても、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。
アレルギーは、体の免疫システムが本来無害な物質に対して過剰に反応してしまうことで起こります。初めてアレルゲンに接触した時は症状が出なくても、体がそのアレルゲンを「記憶」し、二度目以降の接触でアレルギー反応を起こすことがあります。これが、「ある日突然、犬アレルギーになることがある」と言われる理由です。長年犬と一緒に暮らしていても、体質や生活環境の変化、ストレスなどが引き金となり、突然アレルギーを発症することもあるのです。
犬アレルギーの重症度は人によって大きく異なります。軽度であればくしゃみや鼻水程度で済むこともありますが、重度の場合には喘息発作やアナフィラキシーショックなど、命に関わる症状を引き起こすこともあります。
残念ながら、現在の医療では犬アレルギーを完全に「完治」させることは難しいとされています。そのため、治療は主に症状を緩和させるための対症療法がメインとなります。しかし、適切な対策と治療を行うことで、症状をコントロールし、愛犬と快適に共存することは十分に可能です。
2.犬アレルギーになっても楽しく過ごすために
もし犬アレルギーを発症してしまっても、適切な対策を行うことで、症状の緩和は十分に可能です。実際、犬アレルギーになってしまった後も、愛犬と暮らしているという方は多くいらっしゃいます。
ここでは、犬アレルギーの症状がなるべく出ないようにする方法をご紹介します。
薬で症状を抑える
アレルギー用の薬を活用し、症状を和らげます。
投薬によるアレルギー症状の軽減は、アレルギーの治療法として、もっとも一般的な方法で、アレルギー症状が軽い場合は、これだけでも十分な効果が期待できるでしょう。
市販薬や処方薬には、抗ヒスタミン薬、ステロイド薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬などがあります。
- 抗ヒスタミン薬: アレルギー症状の原因となるヒスタミンの働きを抑え、くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、じんましんなどの症状を和らげます。眠気などの副作用が出る場合もあるため、医師や薬剤師に相談して自分に合ったものを選びましょう。
- ステロイド薬: 炎症を抑える効果が強く、鼻炎スプレーや吸入薬、軟膏など様々な形で使用されます。症状が重い場合に処方されることが多いです。
- ロイコトリエン受容体拮抗薬: 喘息やアレルギー性鼻炎の症状を抑える働きがあります。
これらの薬は症状を一時的に抑えるものであり、根本的な治療ではありません。自己判断で服用を続けたり、症状が悪化したりした場合は、必ず医師の診察を受け、適切な診断と処方を受けることが重要です。また、アレルギー症状を和らげるための「アレルゲン免疫療法」(舌下免疫療法など)も研究・導入されており、長期的な改善が期待できる場合もあります。これは専門医と相談して検討する価値があります。
空気を清潔に保つ
こまめな換気や部屋の掃除、空気清浄機などを活用して、空気を清潔に保ちましょう。
密閉空間にいると、犬アレルギーの症状はどうしても出やすくなります。
犬と過ごす空間を清潔に保つことで、アレルゲンが室内にこもるのを防ぎ、少しでもアレルゲンを吸い込まないようにしてください。
アレルゲンは非常に小さく、空気中に舞い上がって長時間浮遊する性質があります。そのため、室内の空気を清潔に保つことは、アレルゲン暴露を減らす上で非常に効果的です。
シャンプー・ブラッシングの頻度を上げる
シャンプーやブラッシングの頻度を上げ、抜け毛、フケ、ダニなどのアレルゲンを落としましょう。
愛犬の体を清潔な状態に保つことで、犬アレルギーの症状は出づらくなります。
ただし、犬によっては頻繁なシャンプーが負担になることもあるため、愛犬の性格や体調に合わせて取り組むようにしましょう。
犬の体から発生するアレルゲンは、定期的なケアによって大幅に減らすことができます。
- シャンプー: 獣医さんと相談しながら、犬の皮膚に負担をかけない範囲で、週に1回程度のシャンプーを検討しましょう。アレルゲンを洗い流すだけでなく、フケや皮脂の分泌を抑える効果も期待できます。シャンプー後はしっかりと乾かし、湿気でカビやダニが発生しないように注意してください。
- ブラッシング: 毎日こまめにブラッシングを行うことで、抜け毛やフケを室内に飛散させる前に除去できます。特に換毛期には念入りに行いましょう。ブラッシングは屋外で行うか、換気の良い場所で行い、終わったらすぐにアレルゲンを処理することが重要です。
- トリミング: 定期的なトリミングも有効です。毛が伸びすぎるとフケや汚れがたまりやすくなるため、適切な長さに保つことでアレルゲンを管理しやすくなります
生活空間を分ける
最終手段として、基本的な生活環境を分け、アレルゲンに触れる期間をできるだけ減らす方法もあります。
特に寝室へは出入りさせないようにし、すべての部屋で愛犬と過ごすことは避けてください。
その際は、愛犬が寂しくならないように、散歩時間を長くするなどの工夫をしてあげると良いでしょう。
アレルギー症状が重い場合や、他の対策では十分な効果が得られない場合、物理的にアレルゲンとの接触を減らすことが有効です。
- 寝室の独立: 人間が最も長く時間を過ごす寝室は、アレルゲンから完全に隔離することが非常に重要です。犬を寝室に入れないだけでなく、寝室のドアは常に閉めておき、犬の毛やフケが入り込まないように徹底しましょう。
- 特定の部屋への制限: リビングなど、家族が長く過ごす部屋以外は、犬の立ち入りを制限することも検討できます。例えば、犬専用のスペースを設け、そこを犬の「部屋」とすることで、他の部屋へのアレルゲンの拡散を最小限に抑えられます。
- 犬用ベッドや毛布の管理: 犬が使用するベッドや毛布はアレルゲンが集中しやすい場所です。定期的に洗濯し、清潔に保ちましょう。可能であれば、アレルゲンが付着しにくい素材を選ぶのも良い方法です。
- 分離不安への配慮: 生活空間を分けることで、犬が寂しさを感じる可能性があります。散歩の時間を長くしたり、遊ぶ時間を増やすなど、犬との触れ合いの質を上げることで、愛犬のストレスを軽減する工夫が必要です。家族みんなで愛情を注ぎ、犬が安心して暮らせる環境を整えましょう。
3.犬アレルギーの症状
犬アレルギーの代表的な症状には、以下のようなものがあります。
ただ、犬アレルギーの症状には個人差があり、必ずしもすべての症状が出るわけではありません。疑わしい症状がみられたら、できるだけ早く医師の診察を受けましょう。
風邪に似た症状
咳やくしゃみ、鼻水など、風邪に似た症状が現れます。
犬と同じ空間にいる時だけ症状が出る場合には、犬アレルギーの疑いがあるでしょう。
これらの症状はアレルギー性鼻炎の典型的なものです。鼻の粘膜にアレルゲンが付着することで、炎症が起こり、透明な鼻水、連続するくしゃみ、鼻づまりといった症状が現れます。特に、犬と触れ合った後や、犬がいる部屋に入ったときに症状が顕著になる場合は、犬アレルギーの可能性が高いです。風邪と異なり、発熱や倦怠感は通常みられません。
喘息
風邪に似た症状とも少し被りますが、喘息のような症状が出ることもあります。
症状としては、呼吸が苦しい、喘鳴(ぜんめい)など、喘息発作のようなものがみられます。
犬アレルゲンが気道に入り込むと、気管支が収縮して呼吸困難を引き起こすことがあります。喘鳴(ぜんめい)は、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった呼吸音のことで、気道が狭くなっているサインです。咳が止まらない、胸が締め付けられるような感覚、息を吸い込むのが辛いなどの症状も喘息発作の兆候です。喘息は放置すると重症化するリスクがあるため、これらの症状が見られた場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
目の腫れ
目のかゆみ、充血、流涙、まぶたの腫れなどがみられることもあります。
症状が長く続いたり、悪化したりすると、結膜炎を引き起こすこともあるため、気になる場合は医師に相談するようにしましょう。
アレルゲンが目に触れることで、アレルギー性結膜炎を引き起こします。目の異物感、ごろごろ感、光がまぶしく感じる羞明(しゅうめい)などが伴うこともあります。目をこすることで症状が悪化し、細菌感染を併発して二次的な目の炎症を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
蕁麻疹(じんましん)、湿疹
犬と接触した部位や皮膚の柔らかいところに、かゆみ、赤み、腫れなどの症状が現れます。
蕁麻疹や湿疹が粘膜部分に発生すると、呼吸困難を起こすこともあるため、注意が必要です。
犬アレルゲンが皮膚に触れることで、局所的にかゆみを伴う発疹(じんましん)や湿疹が現れます。特に、犬がなめた場所、触れた場所、抱っこした場所などに多く見られます。皮膚の弱い部分や、アトピー性皮膚炎の既往がある人は、より症状が出やすい傾向があります。広範囲にじんましんが出たり、唇や喉の粘膜が腫れて呼吸が苦しくなる場合は、アナフィラキシーの初期症状である可能性があり、緊急の医療処置が必要です。
下痢
症状が悪化すると、下痢などの消化器症状が現れることもあります。
自身でアレルギー症状と気付くまでには時間がかかるため、見逃さないようにしましょう。
犬アレルギーで消化器症状が現れることは比較的稀ですが、体全体に強いアレルギー反応が起こる場合に、下痢や腹痛、吐き気、嘔吐などの症状が見られることがあります。これは、アレルゲンが体内に入り、消化器系の免疫反応を引き起こすためと考えられています。これらの症状が出た場合は、アレルギー反応が全身に及んでいる可能性があるので、速やかに医療機関を受診してください。
呼吸困難
重度の犬アレルギーの場合、嘔吐や呼吸困難などの症状がみられます。
めまい、動悸、嚥下困難などの症状がみられたら、呼吸困難を起こす前触れかもしれません。重いアレルギー症状は命に関わることもあるため、できるだけ早く病院を受診しましょう。
呼吸困難は、アナフィラキシーショックと呼ばれる重篤なアレルギー反応の兆候です。これは、アレルゲンが体内に大量に入り込み、全身で急速かつ広範囲にアレルギー反応が起こることで、血圧低下、意識障害、呼吸困難など、命に関わる症状が同時に現れる状態です。喉の締め付け感、声がかすれる、意識が朦朧とする、顔面蒼白、冷や汗なども危険なサインです。これらの症状が一つでも見られたら、一刻も早く救急車を呼ぶか、緊急で医療機関を受診する必要があります。
4.犬アレルギーかどうかを確認する方法
犬アレルギーかどうかを調べるには、主に2種類の検査方法があります。
プリックテスト
皮膚表面につけた傷にアレルゲンを接触させ、アレルギー反応を確認する方法です。
針で少し傷をつけた皮膚に犬アレルギーのアレルゲンを数滴たらして数十分放置し、皮膚の赤み、かゆみ、腫れがないか観察します。
プリックテストは採血を必要としないため、小さなこどもや赤ちゃんでも受けることができます。
プリックテストは、アレルゲンを直接皮膚に反応させることで、即時型アレルギーの有無を確認できる簡便な検査です。通常、上腕の内側や背中に行われます。アレルゲンを滴下した箇所が赤く腫れ上がったり、かゆみが出たりすれば陽性と判断されます。検査時間は短く、結果もその場で確認できるため、アレルギーの原因を迅速に特定するのに役立ちます。ただし、皮膚の状態によっては検査が難しい場合や、薬の服用によって結果に影響が出る可能性もあるため、事前に医師に相談が必要です。
ラストテスト
血液を少量採取し、「IgE抗体」というアレルゲン反応物質の量を調べる方法です。
IgE抗体が多いほどアレルギーを引き起こす可能性が高いとされ、犬アレルギー以外のアレルギー物質も知ることができます。
ラストテストは、特定のアレルゲンに対して体内でどれくらいのIgE抗体が作られているかを数値で確認する検査です。この検査は、一度の採血で複数のアレルゲンに対する抗体量を調べることができるため、犬アレルギーだけでなく、他のアレルギー(花粉、ダニ、ハウスダスト、食物など)の有無も同時に確認できます。プリックテストができない場合や、より詳細なアレルギー情報を知りたい場合に有効です。数値が高いほどアレルギー反応が強く出る可能性が高いとされますが、数値が高いからといって必ずしも重い症状が出るわけではありません。医師は検査結果と患者の症状を総合的に判断して診断を行います。
5.犬アレルギーが出にくい犬種はいない
基本的に、犬アレルギーの症状が出にくい犬種は存在しません。
犬アレルギーは、犬の抜け毛、フケ、唾液、尿などで発症するため、完全に防ぐことは不可能です。
ただし、アレルゲンのひとつである抜け毛を気にするのであれば、抜け毛が少ない犬種を飼うと良いでしょう。
抜け毛が少ない犬種としては、トイ・プードル、マルチーズ、ヨークシャー・テリア、シーズー、ミニチュア・シュナウザーなどがおります。
「アレルギーフレンドリー」や「低アレルゲン」と謳われる犬種も存在しますが、科学的にはアレルギー症状が出にくい犬種はいないという認識が正しいです。なぜなら、犬アレルゲンの主成分は、犬のフケ、唾液、尿に含まれるタンパク質であり、これらはすべての犬種が分泌しているからです。例えば、抜け毛の少ない犬種でも、舐めることによって唾液がフケに付着し、それが空気中に舞うことでアレルギー反応を引き起こす可能性があります。
しかし、「抜け毛が少ない犬種」であれば、アレルゲンの一つである毛の飛散量を減らすことができるため、結果的にアレルゲンに触れる機会を減らせる可能性はあります。 具体的には、以下のような犬種が挙げられます。
- トイ・プードル: 抜け毛が非常に少なく、シングルコートで毛が絡みにくいため、アレルゲンが飛散しにくい傾向があります。
- マルチーズ: 抜け毛が少なく、シングルコート。定期的なブラッシングが重要です。
- ヨークシャー・テリア: 抜け毛が少なく、絹のような毛質が特徴です。
- シーズー: 抜け毛が少ないですが、長い毛の手入れが必要です。
- ミニチュア・シュナウザー: 硬い毛質で、抜け毛が少ないとされています。定期的なトリミングが必要です。
- バセンジー: 短毛ですが、抜け毛が少ない犬種として知られています。
これらの犬種を検討する場合でも、個体差があること、そしてシャンプーやブラッシングなどの適切なケアが不可欠であることは忘れてはいけません。また、犬を飼う前に必ずアレルギー検査を受け、ご自身の体質と向き合うことが最も重要です。
6.まとめ
犬を飼う前は犬アレルギーの検査をし、アレルギーの有無を確認しておくと安心です。
犬アレルギーは完治が難しい病気ですが、だからといって絶対に犬と暮らせないわけではありません。
発症してしまった場合でも、薬の服用や生活環境を見直すことで愛犬と楽しく過ごすことはできるため、ぜひ積極的に対策を行いましょう。
運営会社:イオンライフ株式会社
最新記事 by イオンのペット葬 (全て見る)
- チワワの終末期に見られる変化と、後悔しないための向き合い方 - 2026年1月31日
- 老犬の最期の呼吸は苦しい?死ぬ前の症状と飼い主ができること - 2026年1月30日
- グッピーの死ぬ前兆とは?突然死を防ぐ原因の見分け方と対処法 - 2026年1月30日
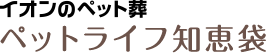

 犬はお留守番中どんな気持ち?分離不安障害には気を付ける
犬はお留守番中どんな気持ち?分離不安障害には気を付ける 犬に気持ちは伝わる~愛犬の気持ちを知って絆を深めよう~
犬に気持ちは伝わる~愛犬の気持ちを知って絆を深めよう~ 【犬の吠え】しつけで無駄吠えをなくす方法とポイント
【犬の吠え】しつけで無駄吠えをなくす方法とポイント 犬の寝る姿勢でわかる!リラックスしている寝相と注意したい寝相
犬の寝る姿勢でわかる!リラックスしている寝相と注意したい寝相
