うずらの寿命は平均何年?飼育のコツと死ぬ前の兆候を解説
2025.10.16 小鳥目次
うずらの寿命は平均何年?飼育のコツと死ぬ前の兆候を解説
ウズラは小さな体で愛らしい姿からペットとして人気がありますが、その寿命は飼育環境に大きく左右されます。
適切な知識を持って世話をすることが、健康維持と長生きにつながる大切なポイントです。
この記事では、うずらの平均的な寿命の目安、健康を保つ具体的な飼育のコツ、注意したい病気のサイン、そして寿命が近づいたときに見られやすい兆候を解説します。
万が一の際に備え、安置や供養の方法もあわせて紹介します。
うずらの平均寿命は7〜8年が目安
ペットとして飼育されるうずらの平均寿命は、一般的に7〜8年が目安とされます。
ただし個体差や環境により幅があり、栄養管理やストレスの少ない環境づくりができれば10年以上生きる例もあります。
一方、野生のうずらは天敵や厳しい自然環境の影響で1〜2年と短命です。
日本で飼育されることの多いヒメウズラや並ウズラでも、適切な環境下ではこの目安に近い年数を生きることが期待できます。
うずらを長生きさせるための5つの飼育のコツ
長寿の鍵は、毎日の丁寧なケアを安定して続けることです。以下の5つは特に重要な基本です。
1. 栄養バランスの取れた食事を与える
主食はうずら専用フードが適しています。必要なタンパク質・ビタミン・ミネラルがバランスよく配合されています。
副食として小松菜・豆苗・ニンジンなどの野菜を少量。
ほうれん草はシュウ酸が多いため避けます。産卵するメスはカルシウム不足になりやすいので、ボレー粉等を別容器で常備します。
人の食べ物、ネギ類・アボカドなど有害な食材は与えないでください。食事内容に不安がある場合は獣医師に相談を。
2. ストレスの少ない静かな環境を整える
うずらは臆病で音や振動に敏感です。テレビやドアの開閉音が少ない落ち着いた場所にケージを設置しましょう。
上方からの急な動きに驚いて跳ね上がる事故を防ぐため、設置場所と接し方に配慮します。
多頭飼育は相性やスペースに注意し、必要に応じてケージを分けるなどの対策を。
3. 定期的な日光浴で健康を維持する
日光浴により体内でビタミンD3が作られ、カルシウム吸収を助けます。
週に数回、1回15分程度を目安に。網戸越しや屋外の安全な場所で行い、真夏は必ず日陰を併設して自発的に体温調節できるようにします。
窓ガラスは紫外線を通しにくいため、必要に応じて小動物用UVライトの活用も検討します。
4. 産卵の頻度をコントロールする
頻繁な産卵は体の負担となります。つがい飼育ではオスの存在が刺激となって産卵が増えやすいため、別居も選択肢です。
日照時間が13時間超で産卵が促進されるため、照明時間を調整しメスの負担を軽減します。卵の採取を目的としない場合は特に配慮を。
5. 飼育ケージは常に清潔に保つ
フンや食べこぼしは感染症のリスクになります。
床材(新聞紙・ペットシーツ・ウッドチップ等)は毎日交換、フン切り網もこまめに清掃。
餌入れ・水入れは毎日洗浄し新鮮な餌と水を提供。月1〜2回はケージ全体を水洗い・天日干しで乾燥させ衛生を保ちます。
注意!うずらが罹りやすい病気と体調不良のサイン
うずらは体調不良を隠す傾向があるため、異変に気づいた時には進行していることもあります。
日頃から食欲・フンの状態・行動の変化を観察し、気になる点が続く場合は早めに動物病院へ。
下痢や食欲不振は消化器系の病気の可能性
健康なフンは白色(尿酸)と暗色(便)がはっきり分かれます。
水っぽい・形が崩れる・色が異常などはサインです。古い餌や不衛生な水、ストレス、急な温度変化が原因となることがあります。
下痢と食欲低下が同時に見られるときは早めに受診しましょう。
そのう炎の症状と原因
食道の一部「そのう」で細菌・真菌が増殖して炎症が起きる病気です。
粘りのある吐き戻し、未消化の餌の嘔吐、食欲不振、そのうの膨満、首振りなどが見られます。
餌・水の毎日交換と清潔維持が予防に有効です。症状がある場合は自己判断を避け、獣医師の診察を。
寄生虫による健康被害と予防策
内部寄生虫(回虫等)は下痢・食欲不振・体重減少、重度では栄養不良や腸閉塞の恐れ。
外部寄生虫(ダニ等)は貧血・かゆみ・羽の損傷の原因に。
新しく迎える個体はすぐに同居させず、一定期間検疫して健康確認を。清潔維持が最も有効な予防策です。
うずらが死ぬ前に見せる老化や弱っている兆候
年齢や体力低下に伴い、次のような変化が見られることがあります。これらに気づければ、より穏やかに過ごせる環境づくりや心の準備がしやすくなります。
動きが鈍くなり、うずくまる時間が増える
活動量の低下、物音への反応の鈍化、睡眠時間の増加など。
病気でも同様の所見が出るため、食欲・フンの状態と併せて観察し、変化が続けば受診を。
羽のツヤがなくなり、毛づくろいをしなくなる
羽のツヤ低下・乱れ・抜けやすさの増加は体力低下のサインです。
換羽期でないのに抜けが多い、回復が遅い場合は体調の変化を疑います。
食欲が落ちて体重が減少する
食べる量の減少、体重の低下(胸骨が尖って触れる等)。
無理な強制給餌は避け、ふやかした餌や栄養価の高い補助食を少量から試すなど、負担の少ない方法を検討します。併せて飲水を確認しましょう。
もしもうずらが亡くなってしまったら?安置と供養の方法
つらい状況でも、落ち着いて対応できるよう手順を知っておくと安心です。
まずは体を清めて適切に安置する方法
亡くなっていることを確認したら、体が固まる前にまぶたや口をそっと閉じ、手足を自然な姿勢に整えます。
湿らせたガーゼ等で体の汚れを優しく拭き取ります。
ティッシュやタオルを敷いた箱に静かに寝かせ、タオルで包んだ保冷剤やドライアイスをお腹や背中付近に当てて体を冷やし、体をきれいに保つようにします。
直射日光を避けた涼しい場所で、供養の方法が決まるまで安置します。
火葬や埋葬など悔いのない供養の選択肢
供養にはいくつかの方法があります。
火葬はペット専門の葬儀業者に依頼し、合同火葬・個別一任火葬・個別立会火葬などから選べます。
埋葬は、自治体の規定で認められている地域であれば自宅の庭等に行うことも可能ですが、衛生面や動物に掘り返されない深さなどの配慮が必要です。集合住宅ではプランター葬という方法もあります。
なお、ペットとして飼育されていた小鳥(うずら等)の火葬に対応している霊園・葬儀社もあります。家族の気持ちに寄り添い、納得できる方法を選びましょう。
まとめ
うずらの平均寿命は7〜8年が目安ですが、環境次第でそれ以上生きる可能性もあります。
栄養バランスの取れた食事、静かでストレスの少ない住環境、定期的な日光浴、産卵負担の軽減、そして清潔の徹底が長寿の基本です。
日々の観察で病気や老化のサインに早く気づき、必要に応じて獣医師に相談しましょう。
万が一の別れの時にも、落ち着いて安置・供養の方法を選び、感謝の気持ちで見送ることが大切です。
最新記事 by イオンのペット葬 (全て見る)
- 犬の花粉症は皮膚のかゆみがサイン?症状・原因と対策を解説 - 2026年1月19日
- 猫の花粉症の症状と対策|くしゃみや皮膚の痒みはサイン?治療法も解説 - 2026年1月19日
- 犬が最期に鳴くのは苦しいから?理由と意味、老犬を安らかに見送る方法 - 2026年1月19日
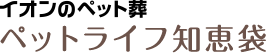
 インコの寿命は平均何年?ボタンインコなど種類別の特徴や重篤時のサインを解説
インコの寿命は平均何年?ボタンインコなど種類別の特徴や重篤時のサインを解説
